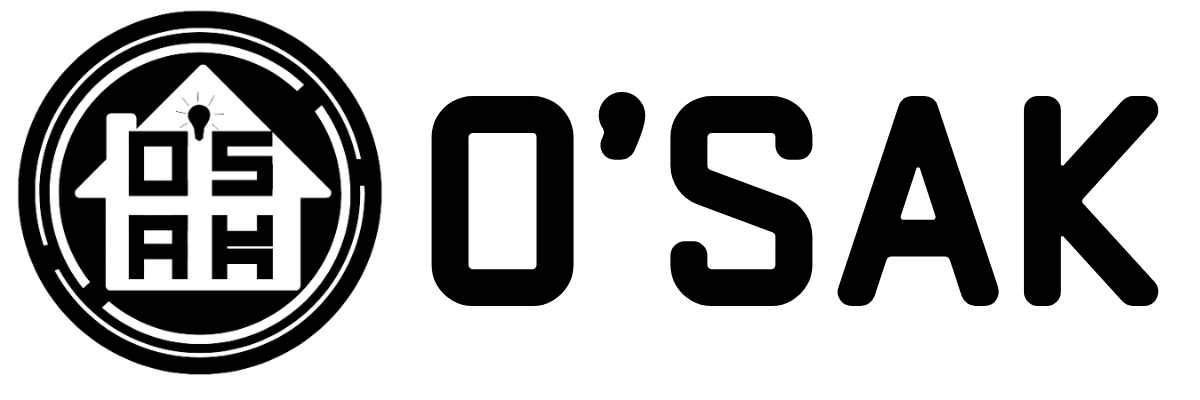家の工法に関してプロ任せの皆さん!!
アミーゴ小池です!!
今回は『工法の決め方』に関してです!
工法は本当に大切です…
皆さんの家の工法をシッカリ学んでください!
今回皆さんに学んでいただきたいのは『工法(こうほう)』です!
構造(こうぞう)ではないので注意してください!
構造に関して知りたい方は下記のオサックで学べますのでご確認を!
てか、工法(こうほう)って何?って思いますよね?
加えて勘の良い方に関しては構法(こうほう)と同じ?って思っている人もいるのでは?
まず初めに工法と構法の違いを簡単に説明します。
・工法:建物全体の構造をどのような部材を使って建てるかと言う事
・構法:建物全体または一部がどのような部材を使って建てられているかと言う事
はい!意味わかりませんよね?同じじゃんって思いますよね?
一般的には『工法』は【施工方法】を示し、『構法』は【部材構成】を表す表現です。
今回皆さんに契約前に必ず確認いただきたい【施工方法】を認識いただきたかったので『工法』です!
回りくどい説明になりましたが、結論から言うと工法の種類を皆さんに理解いただいてから家造りを行う会社を検討した方が絶対に良いです!
施工店や設計事務所では自分達が得意としている工法が世界で一番良い!と営業をしてきます。
しかし断熱材でも外壁材でも屋根材でも床材でも家造りに関わる全ての材料や作り方に『絶対に良い』は存在しません!!!!!
絶対に良い商品があるのであれば日本全国全ての施工店が同じ商品を使います。
世界で一番良い工法があるのであれば日本にこんなに多くの工法で家を造っている会社は有りません!
皆同じ工法で家を造ります!
だからこそ、そんな営業トークに踊らされないで、皆さん自身が費用と性能とデザインを理解して契約する会社が選べるように工法に関しては契約前に必ず学ばなければいけないのです!
最後にお知らせする工法の決定に関しては賛否両論の御意見をいただくのですが、是非とも確認いただきたい内容ですので、面倒でも是非最後まで読み進めてください!
そして今回のオサックは情報量が多いため2分割でお知らせ致します!
カナリ重要な内容なのでシッカリと内容を把握していただきたいです!
前置きが長くなりましたが、さっそく初めて行きます!
■工法の種類が多い訳
日本には様々な工法があります。
ナゼ多くの工法があるかと言うと理由は様々ありますが、簡単に説明すると下記の通りです。
①地震が多い国だから!
日本は地震が多い国です。
日本で生まれて日本で生活している人の場合は多少の震度の地震であれば日常茶飯事ですが、外国では地震が全くない国もあるため驚かれる事が多いのです!
そんな地震に対応する為に様々な工法が産まれたという事です。
②様々な広さ、高さの建物がある国だから!
日本は世界的に見ても恵まれている国です。
東京や大阪などの都心部では高層ビルやタワーマンションが建ってますよね?
更に面積が大きな競技場や大規模な工場の建物など様々な種類の建築物が建てられている国です。
このように建物の広さや高さによって対応する工法が異なるため、多くの工法が日本で取り入れられているという事です。
③他社との差別化
日本では戦後から新築住宅を造り続ける文化が長く続いています。
別のオサックでもお知らせしましたが、先進国で新築を造り続けている国は日本だけです…
そんな新築大好き国の日本で多くの施工会社は同じ工法で造り続けると他社との差別化が出来ず価格競争だけになってしまうため、新しい工法を取り入れて他社との差別化を行う事に努めた結果として多くの工法が誕生しました。
上記に関してはアンチなコメントが入りそうですが、基本的には多くの工法が採用される事に私は否定的ではありません。
むしろ日本の建築のレベルが上がる事なので大歓迎です!
しかし!
地震が多いから●●工法はダメ!
〇〇工法は時代遅れ!
上記のような情報配信や営業方法を聞くと、カナリ残念に思います…
言っている本人は本心から上記のような事を皆さんに伝えるのだとは思いますが、何度も言いますが絶対に、この工法が良い!という工法があるのであれば日本全国の施工店が、その工法を採用しています。
地震が多く、経済的にも発展して、更には研究熱心な会社が多いから様々な工法が産まれただけで、日本では採用してはダメな工法は無く、更には最新の工法にしなければならない理由も無いのです!
お客様である皆さんが、それぞれの工法のメリットとデメリットを理解して購入することが重要です!
では日本で扱われている工法をお知らせ致しますね!
■工法の種類
工法の種類をお知らせするのに簡単に下記のような内容でお知らせ致します。
工法のそれぞれの特徴となる項目を先ずはご確認いただければと思います。
次の項目で費用や耐震性・メンテンナンス性などに関しては詳しくご説明致します。
・メインとなる素材
工法は柱や梁など建物を支えるためのメインとなる素材によって呼び名が異なります。
どんな素材で作られているのかをお知らせ致します。
・改良工事の有無
メインとなる素材が異なるため、建物の重さが工法によってカナリ異なります。
地震が多い日本では建物が重いと地盤を補強する必要が出てきます。
地盤補強や地盤改良はコストに反映する為、工法によって地盤改良が必要なのかどうかは重要なポイントです。
・防火性
家は人の命を守るための建築物です。
火災に強い家は万が一にも隣家が火災になったとしても自分達の家や家族の命を守るために重要な指標です。
・地震の揺れ
地震大国日本では地震に対しての性能は重要視されます。
後半でお知らせ致しますが、この項目では一般的に言われている工法別での評価をお知らせ致します。
・耐久性
オサックでは将来的に家を売却する、または資産価値が残る家を皆さんに造ってもらう事を考えて情報をお知らせしております。
上記の内容より耐久性は大変重要な指標です。
しかし、皆さんがメンテナンスなどを怠ればお知らせする年月まで建物は残らないので注意してください。
・耐用年数
躯体としてどの程度の期間を耐える事が出来るのか?を示した年数です。
しかし施工する業者や基準によって異なるため、ある程度の参考として御認識ください。
ではそれぞれの工法に関して御紹介致します!
■鉄筋コンクリート造(RC造)
〇素材
鉄筋を加工してコンクリートを流し込んで施工する
〇改良工事の有無
地盤改良は必要
大型の基礎と建物自体が重いので地盤の弱い地域では改良費用が多くかかる
〇防火性
耐火構造にするのは容易であり火に強い躯体の工法
〇地震の揺れ
4階建て程度の住宅であれば問題ない。また遮音・防振ともに優れている
〇耐久性
鉄筋とコンクリートの躯体の為、強度・耐久性ともに優れている
〇耐用年数
100~150年
■鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
〇素材
鉄と鉄筋を加工してコンクリートを流し込んで施工する
〇改良工事の有無
地盤改良は必要
大型の基礎と建物自体が重いので地盤の弱い地域では改良費用が多くかかる
〇防火性
耐火構造にするのは容易であり火に強い躯体の工法
〇地震の揺れ
4階建て程度の住宅であれば問題ない。また遮音・防振ともに優れている
〇耐久性
鉄筋と鉄骨・コンクリートの躯体の為、強度・耐久性ともに優れている
〇耐用年数
100~120年
■鉄骨造(S造)
〇素材
鉄で柱・梁を組んで施工する
〇改良工事の有無
地盤改良は必要
比較的軽く地盤改良の費用も抑えられる
〇防火性
準耐火構造にするのは容易な工法で火には適度に強い躯体
〇地震の揺れ
揺れや振動は感じる、強風による振動は上階で感じる
〇耐久性
外装材の性能によるが、躯体としては優れている
〇耐用年数
80~90年
■軽量鉄骨造(LGS造)
〇素材
厚さ6mm以下の鋼材を組んで施工する 軽量鉄骨
〇改良工事の有無
地盤改良は必要
比較的軽く地盤改良の費用も抑えられる
〇防火性
準耐火構造にするのは容易な工法で火には適度に強い躯体
〇地震の揺れ
揺れや振動は感じる、強風による振動は上階で感じる
〇耐久性
外装材の性能によるが、躯体としては優れている
〇耐用年数
50~90年
■木造(2×4工法)
〇素材
工場で木製パネルを制作し現場で壁、床、天井に施工する
〇改良工事の有無
建物も基礎も軽く他の構法に比べると改良費用は一番安く済む
改良が発生しない可能性もある
〇防火性
耐火構造にすることも出来るがカナリのコストがかかる
木材を使用している為、火には弱い
〇地震の揺れ
遮音は考慮が必要だが、揺れはS造、LGS造と比べて同等、もしくはそれ以下の性能
〇耐久性
外装材の性能によるが、木材特有の腐食やシロアリ問題により他の構法よりも耐久性は劣る
〇耐用年数
50~80年
■木造(軸組み構法)
〇素材
木材の柱・梁を組んで施工する
日本で昔から作られている工法
〇改良工事の有無
建物も基礎も軽く他の構法に比べると改良費用は一番安く済む
改良が発生しない可能性もある
〇防火性
耐火構造にすることも出来るがカナリのコストがかかる
木材を使用している為、火には弱い
〇地震の揺れ
遮音は考慮が必要だが、揺れはS造、LGS造と比べて同等、もしくはそれ以下の性能
〇耐久性
外装材の性能によるが、木材特有の腐食やシロアリ問題により他の構法よりも耐久性は劣る
2×4工法とは変わらない耐久性
〇耐用年数
50~80年
■混構造
上記の工法を組み合わせた工法。
RC造+木造や鉄骨造+木造など2つ以上の工法を組み合わせる事でコストの減額や工法のメリットの組み合わせ、更には敷地形状によって採用される工法
構造計算がカナリ複雑になり単体の工法よりも難易度は一般的には高くなる。
混構造の経験が少ない設計事務所や施工店での計画はカナリのデメリットが生じる事が多いため注意が必要。
前半のオサックはココまでです!
既に皆さんの家の工法を決めている人であったとしても学ぶ事はあったと思います。
後半のオサックではより具体的な知識をお知らせ致します。
契約をする前に「本当に自分達の家の工法はコレでいいのか?」と言う事を必ず考えて、納得してから契約をするようにしてください!