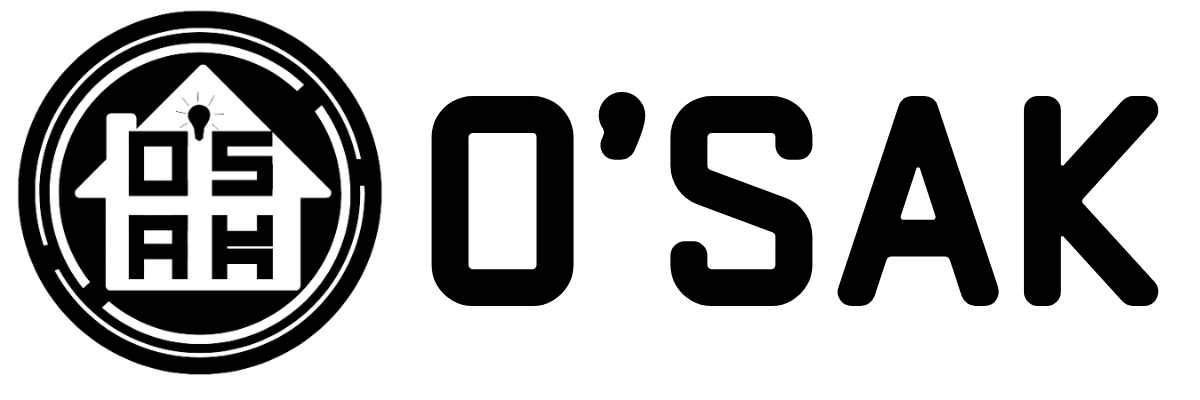土地の法律はプロ任せの皆さん!!
アミーゴ小池です!!
今回は『土地の法律』に関してです!
チョット嫌味な言い方をしましたが法律は大切です…
皆さんの土地の法律をシッカリ学んでください!
今回のオサックを学ぶ前に下記のオサックで先に学んでください!
土地の法律も大切ですが、間取りに関しての簡単な法律を紹介しております!
【契約前】建築法律とルールの基礎:安心できる家造りへのステップ
【契約前】家づくりの法律・ルール完全マスター:最終間取りチェックの要点
そして上記のオサックで間取りに関して注意しなくてはいけない法律は学んだ事を前提で今回のオサックをお知らせ致します。
今回のオサックは土地を購入する前や購入した後に厄介になる法律やルールを御紹介致します!
全ての法律やルールが皆様の土地に適応されるわけではないのですが、今回のオサックを学ぶ事で【土地の『重要事項説明書』確認O’SAK】で御紹介出来なかった法律を理解できると共に、設計の作業が進んだ際も「どの程度の時間がかかるのか?」や「どれだけ大変なのか?」などが理解できます!
それぞれの法律を細かく説明すると物凄い量になってしまうのでカナリ簡略化して説明致します!
■防火地域
火災に対して強い建物を日本では地域によって分けております。
基本的には『指定なし』『準防火地域』『防火地域』の3種類です。
意味合いとしては建物が炎上した際に火が近隣建物に燃え移らない事を考慮した法律なので外壁や屋根などの外部の『火』に対して、どの程度耐えられるのか?を制限した法律です!
デメリットとしては準防火地域や防火地域などの場合は木造住宅の場合は火災に強い建物にしなければならない為、防火性能や耐火認定がとれている外壁や屋根・構法にしなければならない事です。
デザイン的に準防火地域や防火地域で木材のデザインが好きだからと言って『指定なし』の地域のように板張りの外壁仕上げが簡単にできなかったり、窓の大きさに制限が出たりと少々面倒です…
駅や建物が多く建っている地域、高いビルなどが建っている地域は火災が起きた際に被害が大きくなる為、防火性能が高い建物を建てる地域になっている場合が多いです。
各地域の『用途地域』を調べる方法と同じように調べる事が出来ます!
■日影規制(にちえいきせい)
斜線制限とにている法律ですが、一般的には斜線制限をクリアしていれば日影規制もクリアすることが多いです。
建物を建てる事でどのように影が落ちるのか?を計算して規制している数値よりもオーバーする場合は建てる事が出来ない!という法律です!
先に説明したように斜線制限をクリアしていれば『住宅』であれば日影もクリアすることが多いのですが、住宅であったとしても4階建て以上の建物の場合は日影規制によって最上階を小さくしなくてはいけなかったり、建物の形状を変更しなくてはいけない場合があります。
斜線制限だけでは周辺地域に太陽の光を必要十分な量を当てる事が困難な場合に日影規制が検討されます。
東京都内のような首都圏のような建物が混在している地域では、各区により『中高層条例』などの独自な条例を設けて、日影計算を行い近隣住民に説明する義務があったりします。
■市街化調整区域
日本には市街化区域と市街化調整区域の大きく二つの区域があります。
※細かくは非線引き地域もあります。
市街化区域は建物を建てても問題ない地域で各市町村が生活する為の水道や下水などのライフラインを整えている地域です。
建物を促進して建てて良い地域が市街化地域です!
市街化調整区域は上記の市街化区域以外の地域に当たるので、デメリットとしては建物を建てる為の許可が複雑になり、場合によっては建物を建てる許可が出ない…何てこともあります。。。
市街化調整区域の土地を購入することを考えている方がいるのであれば是非とも『建物が本当に建てる事ができるのか?』と言う事を不動産業者さんではなく、建築士さん、または施工業者さんに確認を取ってください!
建てる事はできますよぉ~!や、周りに建物建っているので平気ですよ~!みたいな情報だけでは市街化調整区域はダメです…
場合によっては、その地域の役所に御自身で出向いて自分で聞く事をお勧め致します!
その際に重要なのがコチラ!
・建築指導課、都市計画課のような建築系の課に行くこと
・市街化調整区域で建物が建てられるのか?を確認しに来たことを伝える
・自分は素人である事を伝える
(知識がない、分かっていないプロだと思われると丁寧に教えてくれません…)
・自分が住む家を建てる事を伝える
・どんな事をしたら家を建てる事が出来るのか?家を建てる事が出来ないのか?を聞く
どんな図面が必要で、どんな手続きが必要なのか?などはプロに任せれば良いです!
重要なのは家が建つのか?建たないのか?です!!!
■農地法
農地法は農地に関しては法律です!直接的に建築には関係しませんが、皆さんが家を建てようとしている『土地が農地』だったときに、この法律に触れます。。。
一般的には建物を建てる事が出来る土地は『宅地(たくち)』と呼ばれる土地なのですが皆さんが建てようとしている土地が『農地』だった場合は宅地に変更しなければ建物を建てる事が出来ないのです!
農地から宅地に返る事を『農転(のうてん)』と略して言ったりしますが、地域によっては農転が出来なかったり、協議に時間がカナリかかったりします…
皆さんの土地が農地なのかどうか?を確認するよう方法としては不動産業者さんのようなプロに確認するか『土地の登記簿謄本』を法務局で取得してください!
登記簿謄本には土地の種別が記載されており、その土地の種類が記載されてます!
地方の土地で良くあるのですが、土地を購入しようとしてネットで土地を探していたら同じ地域でも激安の土地があった場合は農地である事が多いです。。。
家を建てる事を明確に不動産業者さんに伝えればプロとして家が建てられるか?農転が出来るのか?農転の費用は幾ら程度なのか?を教えてくれますが…
悪意がある不動産業者さんや知識がない不動産業者さんだと、よくわからずに土地を販売する人もいます…
■地区計画
地区計画に関しては全ての地域で同じルールではない場合が多いです。
その地域によって内容が異なる事が多いですが、最も面倒なのが『外壁後退』です。
外壁後退とは『敷地境界線・道路境界線から一定の距離に建物の外壁を建ててはならない』という決まりです。
簡単に言うと外壁後退がある場合は、外壁後退がない地域よりも建物を小さく建てなくてはならない…って事です。
場合によっては建蔽率や容積率を使い切る事も出来ません…
土地に『空地』を多く作る事が目的なのが地区計画です。周辺環境に『空地=庭』が多く魅力的な地域ですが、思ったよりも建物が小さくなることがあるので注意してください!
■風致地区(ふうちちく)
風致地区は本当に面倒です…
先にお知らせした地区計画のバージョンアップという感じです。
外壁後退などもある事が多いですが、何と言っても『周辺の建蔽率・容積率よりも小さい値』にされてしまいます…
簡単に言うと風致地区ではない隣の地域が建蔽率50%容積率100%だったとしても風致地区の場合は建蔽率40%容積率80%などのように数字を下げられてしまいます…
よってカナリ小さな建物になってしまいます…
風致地区に建物を建てる場合は事前に建物の大きさを確認することを強くお勧め致します!
■景観法(けいかんほう)
景観法がある地域は見た目を気にする地域です!
建物の形や外壁の色などに厳しい規制があります…
自由なデザインや使いたい外壁を使う事が出来ません…
セブンイレブンやローソンのようなコンビニの看板さえも制限する位に厳しいルールです。
文化的に街並みを大切にしたい地域に多く設定されてます!
外壁や外観にコダワリタイ人は避けた方が良いかもしれませんね…
■埋蔵文化保護法
文化的に重要な土器や遺跡が土地に埋まっている可能性がある地域に設定されてます。
申請方法などは何も難しくはなく、土地を掘削して文化的に重要なモノが見つからなければ問題ないのですが…
万が一…文化的に重要なモノが見つかってしまうと大変です…
土地の調査や考古学的に重要な文化財が埋まっている可能性があるため皆さんが、どんな都合や要望を出したとしても調査が終わるまで家を造る事が出来ません…
関東で有名な場所としては鎌倉などが有名ですが、土器などが見つかり今まで発見されたことがない土器などの場合は調査に数カ月もかかる場合があります…
埋蔵文化保護法が設定されている地域が全て土器が出るわけでは無いのですが、皆さんの土地が文化財が発掘されやすい地域なのか、どうか?を確認する事をお勧め致します!
■都市計画道路
都市計画道路が計画されている土地の場合でも建物を建てる事は出来ます!
都市計画道路とは将来的に道路を造る計画があるって事なのですが、道路がすぐに計画されるわけではないので建物を建てる事が出来ます!
しかも、都市計画道路が計画されていない土地と比べると安く購入できる場合が多いです!
しかし…将来的に道路を造る計画があるのでデメリットもあります…
地下工事NG 高い建物NG RCなどの解体しにくい建物NGなど、将来的に道路を造る場合に障害になる建物を建てる事が出来ません…
皆さんの希望する建物が建てられて、計画道路がすぐに計画されない土地であればお買い得かもしれません!
■建築協定
建築協定は完全にその地域限定の決まりです。
周辺住民によって造られた決まりである事が多く、地域によっては様々な決まりがあります。
大きな植栽は切ってはならない。
工事を行っていい時間が厳しく決まっている。
周辺住民にどのような建物なのかを明確に説明しなくてはならない。
などなど…
更に周辺住民によって造られた協定が多いため法律の抜け目を狙った計画やルールの違った解釈を行い建物を計画するなど、今まで紹介したルールの場合は出来た事も全く受け入れられない場合があります…
協定自体がどの程度面倒なのか?を早い段階で認識することをオススメ致します!
以上が今回ご紹介したい土地に関しての法律やルールですが、地域によっては様々な決まりや法律があります…
一般的な法律やルールをお知らせしましたが、皆さんが経験した、他の人にも知って欲しい法律やルールがあれば是非ともお知らせください!